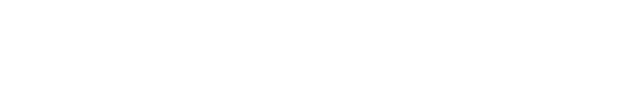【院長ブログ】生活習慣病の最新情報 - 高血圧・糖尿病・脂質異常症の効果的な管理術
今日は多くの患者さんが関心を持たれている生活習慣病について、最新ガイドラインを踏まえてお話しします。
生活習慣病は「静かな病気」と呼ばれることがあります。初期には自覚症状がほとんどないため見過ごされがちですが、放置すると心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な合併症を引き起こす可能性があります。しかし、適切な知識と管理方法があれば、十分にコントロール可能な疾患でもあります。
2025年高血圧ガイドライン改訂のポイントと日常管理法
2025年7月に日本高血圧学会から「高血圧管理・治療ガイドライン2025(JSH2025)」が刊行される予定です。今回の改訂では、名称が従来の「高血圧治療ガイドライン」から「高血圧管理・治療ガイドライン」に変更されました。これは、高血圧になってから治療するのではなく、血圧が上がる前から「管理」することの重要性を強調したものです。
診断基準は従来通り140/90mmHg以上、75歳未満の降圧目標は130/80mmHg未満で変更はありませんが、家庭血圧の測定が今回のガイドラインでもより重視されています。測定方法は朝起きてから1時間以内、トイレを済ませた後で朝食前に測定すること、夜は就寝前に測定し、それぞれ2回測定して平均値を記録する方法が推奨されています。
糖尿病の最新治療と血糖値コントロールの実践術
血糖値管理で便利な指標が、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)という数値です。これは過去1〜2ヶ月間の平均血糖値を反映する指標で、一般的には7.0%未満を目標とします。ただし、高齢の方や他の疾患をお持ちの方では、個別に目標値を設定する場合があります。
糖尿病の食事管理では全体のカロリーだけではなく「食べる順番」も注意します。野菜→タンパク質(肉や魚)→炭水化物(ご飯やパン)の順番で食べることで、血糖値の急激な上昇を抑制できます。また、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂取することも効果的です。
最近は血糖値の自己測定器や連続血糖測定器の普及により、患者さん自身が血糖値の変化をリアルタイムで把握できるようになりました。これにより、どの食品がどの程度血糖値を上げるかを個人レベルで理解し、より精密な血糖管理が可能になっています。
コレステロール・中性脂肪を下げる食事療法の基本
脂質異常症の管理においては、2022年版の動脈硬化性疾患予防ガイドラインが現在の標準となっています。このガイドラインでは、高血圧や糖尿病、喫煙、年齢などに応じて個別にLDLコレステロール(悪玉コレステロール)の管理目標値が設定されています。
合併症のない60歳未満の方はLDLコレステロールを160mg/dL未満、60歳以上の方は140mg/dL未満に管理することが目標ですが、糖尿病の合併症がある方では、LDLコレステロールを120mg/dL未満に管理することが推奨されています。また、すでに心筋梗塞や脳梗塞を起こしたことがある方では、さらに厳しく70mg/dL未満が目標となります。
食事療法の基本は、肉類よりも魚介類や大豆製品を中心とした食事です。魚に含まれるEPAやDHAという成分は、中性脂肪を下げる効果があります。また、卵やレバーなどコレステロールを多く含む食品は控えめにし、代わりに野菜、海藻、きのこなど食物繊維を多く含む食品をしっかりと摂取しましょう。
調理方法も重要で、揚げ物や炒め物は控えめにし、蒸す、茹でる、焼くといった調理法を選ぶことで、余分な脂質の摂取を避けることができます。バターやラードなど室温で固体になる脂肪は特に控えめにし、オリーブオイルなどの植物性油脂を適量使用するようにしてください。
生活習慣病に効く運動療法 - 無理なく続ける秘訣
運動療法は生活習慣病の改善において重要な役割を果たします。運動により中性脂肪が分解され、HDLコレステロール(善玉コレステロール)が増加し、インスリンの働きも改善されます。
運動療法の基本は「軽い運動を毎日続ける」ことです。ウォーキングや水泳など、全身を使う有酸素運動が特に効果的です。運動の強度は「軽く息が上がる程度」が目安で、隣の人と会話ができる程度の強さが適切です。
厚生労働省の指針によると、歩行と同等以上の身体活動を毎日60分以上行うことが推奨されています。これは一度に60分行う必要はなく、10分ずつ6回に分けても効果は同じです。エレベーターの代わりに階段を使う、一駅手前で降りて歩く、掃除や洗濯で積極的に体を動かすなど、日常生活の中で工夫することが大切です。
ただし、心臓の病気をお持ちの方や動脈硬化が進んでいる方は、運動により心臓に負担をかける可能性があります。そのような場合は必ず医師と相談の上で、適切な運動内容を決めるようにしてください。
お薬と生活習慣改善の効果的な組み合わせ方
薬物療法と生活習慣改善は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。お薬を飲んでいるからといって生活習慣の改善を怠ってはいけませんし、生活習慣を改善しているからといってお薬を勝手に中止することも危険です。
高血圧治療では、まず生活習慣の改善から始めることが原則です。減塩、適正体重の維持、適度な運動、禁煙、節酒といった生活習慣の改善により、血圧が十分に下がる場合もあります。しかし、これらの取り組みを3ヶ月間継続しても目標血圧に達しない場合は、薬物療法の開始を検討します。
糖尿病においても、食事療法と運動療法は治療の基盤となります。これらの効果を最大化するために、必要に応じて経口薬やインスリン注射を併用します。最近では、患者さんの生活スタイルに合わせて、様々な作用機序の薬剤を組み合わせることで、より効果的な治療が可能になっています。
重要なことは、お薬の効果を定期的に評価し、必要に応じて調整することです。生活習慣の改善により薬の量を減らせる場合もありますし、逆に病気の進行により薬を追加する必要がある場合もあります。定期的な受診により、医師と一緒に最適な治療方針を決めていきましょう。
まとめ
生活習慣病の管理は一日にしてならず、継続的な取り組みが必要です。しかし、正しい知識と適切な管理方法があれば、必ず改善できる疾患でもあります。当クリニックでは、患者さん一人ひとりの生活スタイルに合わせた治療方針を提案し、皆様の健康をサポートしてまいります。気になることがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。