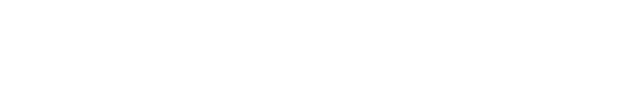【院長ブログ】ALSやパーキンソン病、脳卒中の方に新たな治療選択肢
今回は、ALS(筋萎縮性側索硬化症)やパーキンソン病の患者さんやご家族にとって大きな朗報となる治療についてお話しします。これまで治療選択肢が限られていた流涎(よだれ)に対して、新たな治療法「ゼオマイン」が2025年6月に日本で承認されました。今回は、患者さんの生活の質向上につながる可能性があるゼオマインを使用した治療法について、説明いたします。
慢性流涎とは?原因となる疾患について
慢性流涎とは、意図せずよだれが流れ出てしまう状態が続く病気です。一般的に「よだれ」と呼ばれますが、医学的には流涎症という疾患として扱われます。
慢性流涎の原因は大きく分けて二つあります。一つは唾液分泌量の増加で、妊娠時のつわりや胃炎、口内炎などが挙げられます。もう一つは嚥下機能(飲み込み機能)の低下によるもので、こちらがより深刻な問題となります。
特に神経系疾患が原因となる場合が多く、パーキンソン病、ALS、脳卒中、脳損傷、脳性麻痺、筋ジストロフィーなどが主な原因疾患として知られています。
パーキンソン病では、舌などの動作が緩慢になることで唾液の送り込み障害が起こり、これが流涎の一因となっています。パーキンソン病患者の流涎は、舌の動きが悪くなることで唾液を適切に飲み込めなくなることが研究で明らかになっています。
慢性流涎は患者さんにとって非常に深刻な問題です。意図せずよだれが流れ出てしまうことで、外出を控えるようになったり、会話や食事がしづらくなったりします。また、口の周りに炎症が起きることもあり、日常生活に大きな支障をきたします。
ゼオマインとは?日本初の慢性流涎治療薬
ゼオマインは、A型ボツリヌス毒素製剤という薬剤です。ボツリヌス毒素は、末梢のコリン作動性神経終末に作用し、神経伝達物質であるアセチルコリンの放出を阻害することで効果を発揮します。慢性流涎では、唾液腺に直接注射することで局所的に唾液分泌を抑制し、流涎症状を改善します。
ゼオマインの最大の特徴は、菌体由来の複合タンパク質を含有しない純度の高いA型ボツリヌス毒素製剤であることです。これにより、中和抗体が産生されることによる効果減弱の可能性が低下することが期待されています。
海外では既に70カ国以上で使用されており、慢性流涎以外にも上肢痙縮、痙性斜頸、眼瞼痙攣などの治療に用いられています。日本では2020年に上肢痙縮の治療薬として承認され、その後下肢痙縮、そして2025年に慢性流涎の適応が追加承認されました。
慢性流涎に対するゼオマインの投与方法
慢性流涎に対するゼオマインの投与は、具体的には、耳下腺や顎下腺といった主要な唾液腺に直接注射します。
投与は医師によって行われ、その効果は局所的に発揮するため、全身への影響は限定的です。注射部位は超音波ガイドなどを用いて正確に特定し、安全性を確保して実施します。
効果の持続期間は個人差がありますが、一般的に数カ月間続くとされています。効果が減弱した場合には4ヶ月後に再投与が可能です。
ゼオマイン治療を始めるタイミングと適応
慢性流涎に対するゼオマイン治療を検討するタイミングは、日常生活に支障をきたす程度の流涎症状がある場合です。具体的には、外出を控えるようになった、会話や食事がしづらい、口の周りに炎症が起きるなどの症状が見られる場合が適応となります。
また、ご家族や介護者の負担も考慮すべき重要な要素です。患者さんの衛生面や健康面の管理、頻繁な着替えや洗濯などが大きな負担となっている場合も、治療開始を検討するタイミングといえます。
従来の治療法(経口薬や理学療法など)で十分な効果が得られない場合や、副作用のため継続が困難な場合にも、ゼオマイン治療は有効な選択肢となります。
ただし、治療の適応については、患者さんの全身状態、基礎疾患の状態、他の治療薬との相互作用などを総合的に評価して決定する必要があります。そのため、まずは医師との十分な相談が必要です。
まとめ
これまで治療法の少なかった慢性流涎に対する治療法が増えたことは、これまで悩んできた患者様にとっては新たな光となるのではないでしょうか。慢性流涎でお悩みの方は、一人で抱え込まずに、専門医にご相談いただくことをお勧めします。