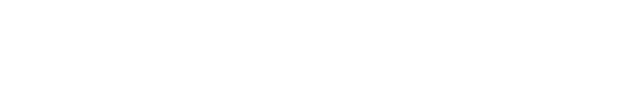【院長ブログ】2025年11月の感染症最新情報〜インフル・コロナ・マイコプラズマへの正しい対処を〜
朝夕の冷え込みが一段と増し、本格的な冬の訪れを感じる季節となりました。最近、当院の外来では「学校でインフルエンザによる学級閉鎖になった」「長引く咳が心配で…」「コロナが職場で流行している」といったご相談を多くいただいております。
愛媛県感染症情報センターが2025年11月7日に発表した最新データ(第44週:10月27日〜11月2日)によりますと、松山市を含む愛媛県内では複数の感染症が同時に流行しており、特にインフルエンザA型が急増し注意報レベルを超えています。また、新型コロナウイルス感染症も依然として全国トップレベルの報告数となっており、マイコプラズマ肺炎も小児から青年層を中心に増加傾向が続いています。
本日は、松山市・東温市・砥部町などの地域における最新の感染症流行状況と、それぞれの感染症の特徴や注意点、適切な受診のタイミングについて詳しく解説いたします。
愛媛県の最新感染症発生状況(2025年11月)
愛媛県感染症情報センターが発表した第44週(10月27日〜11月2日)の定点医療機関からの報告データをもとに、現在の流行状況をご説明いたします。
まず、最も注目すべきはインフルエンザA型の急増です。県全体の定点当たり報告数は第43週の6.59人から第44週には12.78人と、わずか1週間で約2倍に急増し、注意報の基準値である10人を超えました。特に西条保健所管内では警報レベルの39.83人、松山市保健所管内でも11.27人と注意報レベルに達しており、保育所や幼稚園、学校などでの集団感染が懸念されています。
次に、新型コロナウイルス感染症も依然として注意が必要です。第44週の定点当たり報告数は4.57人と、前週の4.92人からは若干の減少を示していますが、実は愛媛県は全国47都道府県の中で最も定点当たり感染者数が多い状況が続いています。松山市医師会の週間疾患情報でも11月第1週に増加傾向が報告されており、油断はできません。
マイコプラズマ肺炎については、松山市医師会の報告では横ばいで推移しているものの、小児から青年層を中心に陽性者が継続的に確認されています。長引く咳や発熱が特徴的で、通常の風邪とは異なる経過をたどることが多い感染症です。
加えて、RSウイルス感染症も第43週の1.05人から第44週には2.15人へと倍増しており、特に四国中央保健所や西条保健所管内で急増しています。生後6ヶ月未満の乳児が感染すると細気管支炎や肺炎などの重篤な症状を引き起こすことがありますので、小さなお子さんをお持ちのご家族は特に注意が必要です。
一方、百日咳については、2025年県内累計で1722例と今年は多くの報告がありましたが、最近は減少傾向にあります。第44週の報告は26例でしたが、依然として10歳未満と10歳代での発症が中心となっています。
インフルエンザA型の流行:今シーズンの特徴と対策
以前のこのブログでお伝えした通り、今シーズンのインフルエンザは、例年に比べて流行開始が早いという特徴があります。愛媛県のデータによりますと、同時期としては過去10シーズンと比較して2番目に多い状況となっており、11月上旬の時点ですでに本格的な流行期に入ったと言えます。
年齢別にみますと、特に6ヶ月から14歳の小児・学童期での増加が顕著で、保育所、幼稚園、小中学校での集団生活を通じた感染拡大が懸念されています。実際に、松山市内でも複数の学校や保育施設で学級閉鎖の報告が出始めています。
迅速検査で型別が判明した症例のうち、99.8%がA型(448件中446件)です。A型インフルエンザは、突然の高熱(38〜40℃)、全身倦怠感、関節痛や筋肉痛などの全身症状が特徴的で、通常の風邪よりも症状が強く現れます。
インフルエンザワクチンの重要性について改めて強調させていただきます。日本感染症学会の報告によりますと、2024/25シーズンのインフルエンザワクチン効果は、米国で56%、欧州で32〜56%、日本の小児では57〜73%と良好な結果が報告されています。ワクチンは感染を完全に防ぐものではありませんが、重症化を予防する効果が明確に示されています。
接種後約2週間で効果が現れ、その効果は5〜6ヶ月程度持続すると考えられています。まだ接種されていない方は、できるだけ早めの接種をお勧めいたします。特に65歳以上の高齢者、慢性呼吸器疾患や心疾患などの基礎疾患をお持ちの方、妊婦の方、小さなお子さんは、重症化リスクが高いため優先的な接種が推奨されます。
受診の目安としては、38℃以上の発熱、強い全身倦怠感、関節痛や筋肉痛などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。発症後48時間以内に抗インフルエンザ薬を服用することで、症状の期間を短縮し、重症化を防ぐことができます。ただし、受診前には必ず医療機関に電話でご相談いただき、他の患者さんへの感染を防ぐための指示に従ってください。
新型コロナウイルス感染症:愛媛県は全国トップレベル
愛媛県における新型コロナウイルス感染症の状況は、依然として注意が必要なレベルで推移しています。2025年第44週の定点当たり報告数は4.57人で、これは全国47都道府県の中で最も高い数値です。2位の新潟県が4.55人、3位の宮城県が4.09人ですから、愛媛県が突出して高い状況が続いていることがわかります。
現在流行している変異株は、オミクロン株の系統に属するXEC系統やLP.8.1系統などです。これらの変異株は、従来のオミクロン株と同様に感染力が高い一方、重症化率は比較的低いとされていますが、高齢者や基礎疾患をお持ちの方では依然として注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症の症状は、発熱、咽頭痛、咳、声がれ、全身倦怠感などで、インフルエンザや一般的な風邪との区別が難しい場合があります。重要なのは、症状が出た場合に自己判断せず、適切に医療機関を受診することです。
感染症法上、新型コロナウイルス感染症は2023年5月に5類感染症に移行しましたが、感染力があることに変わりはありません。厚生労働省の指針では、発症後5日間かつ症状軽快後24時間は外出を控えることが推奨されています。また、発症後10日間が経過するまでは、不織布マスクの着用や高齢者など重症化リスクの高い方との接触を控えるなど、周囲への配慮が求められています。
松山市内でも、高齢者施設や医療機関でのクラスター発生が散発的に報告されています。ご自身が感染した場合は、特に高齢のご家族や基礎疾患をお持ちの方との接触を避け、療養期間中は自宅で安静にすることが大切です。
また、新型コロナワクチンについても、最新の変異株に対応したワクチンが利用可能です。重症化予防効果は明確に示されていますので、特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、定期的な接種を検討されることをお勧めいたします。
マイコプラズマ肺炎:「しつこい咳」にご注意
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマ・ニューモニエという特殊な細菌によって引き起こされる呼吸器感染症です。従来は「オリンピック年に流行する」と言われ、4年周期での流行が知られていましたが、近年この傾向は崩れており、散発的な流行が続いています。
最大の特徴は「しつこい咳」です。初期は乾いた咳から始まり、徐々に湿った咳へと変化していきます。発熱は比較的軽度(37〜38℃台)のことも多く、胸部レントゲン写真で肺炎像が認められても、患者さんご本人は比較的元気であることが多いという特徴があります。これを歩く肺炎(walking pneumonia)と呼ぶこともあります。
患者さんの約80%は14歳以下の小児ですが、青年期や成人での発症も珍しくありません。松山市医師会の報告でも、マイコプラズマ感染症は横ばいながら継続的に報告されており、学校や職場などでの集団感染も見られています。
潜伏期間は2〜3週間と比較的長く、飛沫感染や接触感染によって広がります。家庭内での感染率は5.2〜27.4%と報告されており、一人が感染すると家族内で連鎖的に感染が広がる可能性があります。
診断には、迅速検査キットや多項目同時PCR検査で行っています。特にPCR検査は感度特異度が高く、有用な検査です。治療には、マクロライド系抗菌薬(クラリスロマイシンやアジスロマイシンなど)が第一選択となりますが、近年ではマクロライド耐性のマイコプラズマも増加しており、効果が不十分な場合にはテトラサイクリン系やニューキノロン系の抗菌薬が用いられます。
受診の目安としては、発熱と咳が1週間以上続く場合、特に夜間や早朝に咳が強くなる場合、胸の痛みを伴う場合などは、早めに医療機関を受診してください。適切な抗菌薬治療を受けることで、症状の期間を短縮し、重症化を防ぐことができます。
日本小児科学会が2025年4月に発表した「小児のマイコプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方」では、臨床症状と検査所見を総合的に判断して診断・治療を進めることが推奨されています。当院でも、このガイドラインに基づいた適切な診療を心がけております。
当院の感染症診療と予防への取り組み
うめもとクリニックでは、あらゆる年齢層の患者さんに対する感染症診療を行っております。
複数の感染症が同時に流行している現在、正確な診断と適切な治療が何より重要です。当院では、インフルエンザや新型コロナウイルスの迅速検査キット、多項目同時PCR検査、血液検査、必要に応じて胸部レントゲン撮影などを実施し、症状と検査所見を総合的に判断して診断を行っております。
また、感染症予防の観点から、インフルエンザワクチンをはじめとする各種予防接種も実施しております。特に今シーズンは流行開始が早いため、まだ接種されていない方は、お早めにご相談ください。
高齢者や神経疾患をお持ちの方が感染症にかかると、脱水や発熱による意識障害、既往の神経症状の悪化などのリスクがあります。パーキンソン病、認知症、脳卒中後遺症などで通院中の患者さんは、普段の症状管理とともに、感染症予防にも特に注意が必要です。
当院では、発熱患者さんと一般患者さんの診療時間や待合スペースを分けるなど、院内感染予防対策も徹底しております。発熱や咳などの症状がある方は、受診前に必ずお電話でご連絡ください。適切な受診方法をご案内いたします。
まとめ:感染症予防のために
2025年11月現在の感染症の状況を紹介しました。それぞれの感染症には特徴があり、適切な予防法や受診のタイミングも異なります。しかし、共通して重要なのは、基本的な感染対策の徹底です。こまめな手洗い、適切なマスクの着用(特に発熱や咳などの症状がある場合)、定期的な換気、十分な睡眠と栄養バランスの良い食事などの生活習慣が、すべての感染症予防の基本となります。
感染症のことでご心配なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。正しい知識と適切な対策で、この冬を健やかに過ごしていきましょう。
引用文献
- 愛媛県感染症情報センター「愛媛県感染症情報 2025年第21号(第43、44週)」2025年11月7日 https://www.pref.ehime.jp/site/kanjyo/
- 愛媛県感染症情報センター「インフルエンザ情報(2025/2026シーズン)」https://www.pref.ehime.jp/site/kanjyo/124150.html
- 松山市医師会「週間疾患情報 2025年11月第1週」2025年11月5日 https://matsuyama.med.or.jp/for-residents/disease/
- 日本小児科学会「小児のマイコプラズマ肺炎の診断と治療に関する考え方(2025年4月)」https://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?content_id=142
- 国立健康危機管理研究機構「インフルエンザ流行レベルマップ」https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/020/flu-map.html
- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の感染状況について」2025年11月7日